大学院受験生が知っておきたい「スマホのリスク」と「付き合い方」
「初めてこんなに広範な領域に悪影響が出るものに出会いました。子どもたちの記憶の能力自体にマイナスの影響が出ていると予測されます。極端な話ですけれども、法律によって18歳まではスマートフォンを1時間以上使ってはいけないと、強制的におさえてあげるほうが、未来にとっては幸せであろうと考えます」
ーー東北大学 川島隆太教授 (参照:NHKクローズアップ現代)ーー
スマホは私達の生活に欠かせません。
中学生以上では、スマホを一人一台持っているどころか、人によってはタブレットを含めて2台、3台持っている人も少なくないでしょう。
しかし便利な一方で、スマホを触っていないと不安になってしまう『スマホ依存症』や、スマホの長時間利用の方がなる『脳過労』なども問題になっています。
本記事では、受験生なら知っておくべきスマホのリスクと脳への悪影響を紹介します。
結論から先に言いますが、本気で院試に合格したいなら、スマホは1日に1時間までにしましょう。
スマホで時間が奪われるだけでなく、記憶力や学習意欲の低下をまねく恐れがあります。
まずは、スマホの長時間利用のリスクを見ていきましょう。
スマホの長時間利用は『記憶力低下』『意欲低下』『うつ病』の危険も

おはようございます☀️
— 東大院生くろまあくと@作家・ブロガー🌸『東大院生が実践した 超ショートカット勉強法』重版出来🌸 (@akuto_kuroma) 2019年9月5日
仙台市の中学生2万人以上を対象にした研究では以下のことがわかっています
【スマホ利用が1時間増えるごとに、テストの平均点が5点ずつ下がる】
本気で受験や資格に臨んでいるのであれば
スマホ利用は【1日1時間以内】がおすすめです‼️
スマホの長時間利用による脳への悪影響を示すデータはたくさんあります。
その中の一部を紹介していきます。
スマホの長時間利用はテストの点数を低下させる

仙台市の中学生の『数学の学力とスマホの利用時間の関係』を調査した結果によると、スマホの長時間利用がテストの点数に悪影響を与えていることがわかります。
調査結果のグループは下記の6つに別れており、最も平均点が高かったのが、①と②のグループで、その後はスマホの利用時間が1時間増えるごとにおよそ5点ずつ平均点が下がっていきます。
②:「1時間未満」
③:「1~2時間」
④:「2~3時間」
⑤:「3~4時間」
⑥:「4~5時間」
また、スマホ長時間使用する子どもたちの脳を調べると、脳全体をつなぐ神経線維の集まり、「白質」の発達が遅れていることがわかりました。
さらに、30代~50代のサラリーマンの人たちでも、物忘れが激しくなり、判断力が低下するそうです。
スマホの長時間利用はうつ病のリスクを高め、幸福感を低下させる

ミシガン大学の研究では、Facebookの利用時間が長いほど主観的幸福感が低下することが明らかにされています。
「誰かとつながっていたい」ためにSNSを利用しているのでしょうが、SNSの長時間利用は逆効果で、孤独感や抑うつは強くなります。
SNSの利用時間を30分以下に制限することで、孤独感や抑うつに大幅な改善が見られることもわかっています。
さらに、ピッツバーグ大学の研究では、SNSの利用時間が長ければ長いほどうつ病になりやすいということが明らかにされています。
なんと、SNSの利用時間が長い人は、SNSの利用時間が短い人と比べて、うつ病のリスクは2.7倍高まるそうです。
うつ病は、幸福ホルモンと呼ばれる『セロトニン』の分泌を高めることにより予防できます。セロトニンの分泌を高める方法は以下にまとめています。
夜遅くにスマホを見ると、睡眠の質が下がる

スマホやテレビから出る、青色光
【メラトニン】
体内時計に働きかけ、自然な眠りをサポートするホルモン。睡眠ホルモンとも呼ばれる
みなさんもご存知の通り、スマホからはブルーライトが出ています。
ブルーライトとは、スマホやテレビから出る青色光のことで、ブルーライトを見続けることにより、眠気を誘うメラトニンの分泌と体温の低下が抑制されてしまうことがわかっています。
要するに、スマホを見続けると脳がまだお昼だと勘違いしてしまうのです。
人は、寝ているときに情報を整理し、記憶の定着を強化しています。
そのため、睡眠に悪影響があれば、記憶にも悪影響が出てしまいます。
できれば寝る前2時間はスマホやテレビを完全にシャットアウトすると、スムーズに眠ることができるようになると思います。
『スマホ平均利用時間』と『スマホ依存チェックポイント』

自分がスマホをどれくらい使用しているのかということを把握していない人も多いですよね。
私達は、1日にどれくらいスマホを利用しているのでしょうか。
1日のスマホ平均利用時間は『3時間5分』

ニールセンデジタルの2018年12月の日本におけるスマートフォン利用時間やアプリの利用状況の調査によると、1日あたりのスマホの平均利用時間は『3時間5分』にも及ぶそうです。
ちなみに、2018年の7月に行われた調査ではスマホの平均利用時間は『3時間4分』だったため、ほとんど変化が見られません。
これを見て「自分はそんなに使っていない」と思った人が多いと思います。
しかし、スキマ時間にちょくちょく見ているので、自分で思っているよりもスマホ利用時間が多いはずです。
iPhoneは「スクリーンタイム」機能。アンドロイドは「Digital Wellbeing」機能で自分のスマホ利用時間を確認できるので、ぜひ確認してみて下さい。
『時間の使い方』は『命の使い方』です。
自分が何にどれくらい時間を使っているかは知っておいたほうがいいでしょう。
こんな人は要注意。スマホ依存症の危険も!
5つ以上あてはまるのであれば、依存症予備軍といえるでしょう。
院試の受験勉強中は、脳への悪影響も考慮すると、3つ以下に抑えるのが好ましいです。
難関大学を目指すのであれば1つ以下になるように、スマホとの付き合い方を変えましょう。
まとめ:スマホとの付き合い方が受験結果を左右する
いかがでしたでしょうか。
スマホの長時間利用による学習効率への悪影響は計り知れませんが、スマホ自体はかなり便利で私達の生活に欠かせないツールです。
しかし、スマホと上手に付き合えている人がほとんどいないのが現状だと思います。
例えば、勉強の息抜きにスマホを触る人は多いですが、これは、直前の勉強内容の記憶定着を妨害する行為です。
スマホをみることで脳に膨大な量の情報が入ってくるため、勉強の合間にスマホを見ることはNGです。
※こちらの記事で解説しています
スクリーンタイムやDigital Wellbeingで自分のスマホ利用時間をチェックし、1日の利用時間が1時間を超えていた場合は、成績に悪影響が出ているおそれがあります。
スマホの長時間利用は、記憶力低下をまねくだけじゃなく、うつ病のリスクを高め、幸福感を低下させる恐れもあるので、スマホの利用は1日1時間以内に抑えるのがよいでしょう。
スマホと上手に付き合い、ぜひ第一志望に合格することをお祈りしています。
【東大院試サークルESCAPEって?】難関大学大学院を目指す人へ
【覚悟のない人閲覧禁止】英語学習のモチベーションを100倍に上げる方法
【ドーパミン×勉強】東大院生おすすめの脳に逆らわない勉強法
【大豆製品は頭にいい?】調べたら豆腐や納豆は超優秀な育脳食でした
【東大生おすすめ】テレビを観る時間を減らし、作業時間に充てる方法4選
【生産性を10倍にする】マルチタスクからシングルタスクへ
【睡眠と脳の関係から考える】『睡眠前学習』暗記法
【東大院生おすすめ】効果の高い勉強法10選【場所やアイテムも】
【東大院生おすすめ】勉強に必須のアイテムTOP3を紹介!
【パワーナップ】脳のパフォーマンスを上げる一流の『睡眠法』
【東大院生おすすめ】実生活ですぐに使える心理学7選
【パブロフの犬】一瞬で集中モードに切り替える『条件反射法』3選
【くろまあくと著のおすすめ書籍】
『手間は最小。成果は最大』効率よく学びを結果に結びつける方法を紹介しています。
参考文献
ニールセンデジタル『スマートフォンの利用時間やアプリの利用状況などに関するレポート』
NHKクローズアップ現代『“スマホ脳過労” 記憶力や意欲が低下!?』






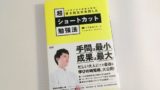



>>HOME画面に戻る
>>勉強法の記事一覧へ進む