「勉強がしたくない」学習性無力感から抜け出す
・ 「何をやってもうまくいかない」という思いこみにより、行動を起こす気がなくなってしまうこと
「どうせうまくいかないんだ」と自分自身で思い込んでいると、なにもやる気が起きなくなってしまいます。
これを、学習性無力感といいます。
勉強のやる気が起きない人は、(程度に差はあれど)学習性無力感に陥っている可能性があります。
学習性無力感とは、行動の無意味さを学習している状態。
「無理やり行動しよう」としても、思うように身体は動きません。
学習性無力感から抜け出すためには、学習性無力感から抜け出すための対策をとる必要があります。
「勉強したってどうせ成績は上がらないよ」
「私には、この大学に合格することはできないよ」
「私には、この資格を1ヶ月で取得するなんて無理だよ」
自分ができないと思っていることをできるはずがありません。
自分ができないと思っていることのための努力は苦痛でしかないでしょう。
しかし、少しづつ成功体験積み重ね、少しづつポジティブに変わることで、誰でも勉強で思うような結果が出せるようになります。
私も昔は勉強が大の苦手で、「どんなに勉強しても平均点もとれない」と思いこんでいた経験がありました。
しかし、今では東京大学大学院に合格し、勉強本もいくつも執筆しています。
人より遥かに効率よく勉強できる自信もあります。
私が変わったのですから、誰でも、絶対に、勉強が得意になれるのです。
それでは早速、学習性無力感に陥りやすい人の特徴と、学習性無力感から抜け出し、勉強が得意になる方法を紹介していきます。
学習性無力感になりやすい3つのタイプとタイプ別対応法

①タイプ:自己否定された経験がある
対処法:小さな成功体験を積み重ねる
②タイプ:完璧主義
対処法:ほどほどに力を抜くことを覚える
③タイプ:生活リズムが乱れている人
対処法:睡眠時間をきちんと確保する
学習性無力感になりやすいタイプは、大きく分けて3つです。
1つ目は、自己否定された経験がある人。
2つ目は、完璧主義の人。
3つ目は、生活リズムが乱れている人。
複数当てはまる人は、とくに要注意です。
それでは、それぞれ詳細を見ていきます。
自己否定された経験がある人は、小さな成功体験を積み重ねる

「あなたは頭が良くないんだから、人一倍努力しなさい」
「うちの子は〇〇くんと違って頭が良くないんですよ」
「この子はあたしに似て、数学が苦手なのよ」
「こんな問題も解けないの!」
親にこのように言われた、あるいは言っているのを聞いたことがあるという人は少なくないのではないでしょうか。
日本人は周囲を立て、必要以上に謙遜します。
そして、それを美徳とする文化があります。
子どもの持っている世界は、得てして大人よりも狭く、まして親の価値観はほとんどそのまま子に伝染してしまいます。
「うちの子は勉強ができない」と言われながら育った子どもが、勉強が得意になるなんてことはほとんどないでしょう。
心理学でラベリングという言葉があります。
これは、「あなたって〇〇だよね」と決めつけるようにラベルをはると、本人はそのラベルのとおりに行動してしまうというものです。
親に「勉強できない」と聞かされて育てば、子どもが勉強ができないようになってしまうのは自然の流れです。
このようなタイプは、「どうせやっても無駄だから」と学習性無力感に陥りやすくなります。
対処法としては、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。
- 1教科だけにしぼって、試験でいい点数を取ってみる
- 今よりもっと簡単な勉強から始める
などが効果的です。
例えば、1教科、あるいは1分野に絞って集中的に対策をすると、すぐに結果に現れます。
すると、「勉強したら結果が出た」という成功体験に繋がります。
あるいは、二次関数で躓いたとしたら、一次関数の解ける問題から勉強を始めれば、勉強を始めるのは苦ではなくなります。
勉強は能力や才能ではありません。
もし今まで、「あなたは勉強できない」と言われ続けていたとしても、それはあなたのせいではなく、環境のせいです。
少し正しい勉強法を知るだけで、あなたは絶対に「勉強が得意だ」と胸を張って言えるようになります。
他人は所詮他人。
あなたを正しく評価することなどできないのですから、否定されたことなどかけらも気にせず、小さな成功のために行動を開始しましょう。
子どもや自分のやる気を高める方法は、こちらの【ピグマリオン効果】子どもや自分の勉強の意欲を高める方法の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
完璧主義の人は、ほどほどに力を抜くことを覚える

2つ目の学習性無力感になりやすいタイプは、完璧主義の人です。
- 細かいところまで全部やらないと気がすまない
- 完璧な計画や完璧な準備がないと気がすまない
- 1から順番に始めないと気がすまない
このような完璧主義タイプは、人一倍頑張ることができるにも関わらず、努力が空回りしてしまい、結果が出ないことがあります。
私は、完璧主義の反対は効率主義であると考えています。
・ 『努力の量と成果の量は一致する』と考えている
・ 細かいところも手を抜くことができない
【効率主義】
・ 『楽して大きな成果を生み出したい』と考えている
・ 重要でないと感じたら手を抜く
完璧主義の人であれば、問題集を1から順番に解いていこうとするでしょう。
しかし、効率主義の人は、試験に出やすい問題から重点的にとき、必要のない問題は解くことすらしません。必要がないと感じたら、全力で力を抜きます。
習慣化コンサルタントの古川武士さんが書いた、『2割に集中して結果を出す習慣術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)では、次のように述べています。
- 完璧主義が効率を下げる
- 過剰な完璧主義はビジネスでは弊害になる
このように、「完璧でなければいけない」という思い込みは、ときに勉強やビジネスの妨げとなります。
力を抜くことは決して悪いことなのではなく、むしろ、大事な場面で100%の力を発揮するためにはとても重要であるということを覚えておきましょう。
完璧主義をいますぐにやめるべき理由は、こちらの2つの記事で紹介しています。ぜひ合わせてチェックするようにしてください。


生活リズムが乱れている人は、睡眠時間をきちんと確保する
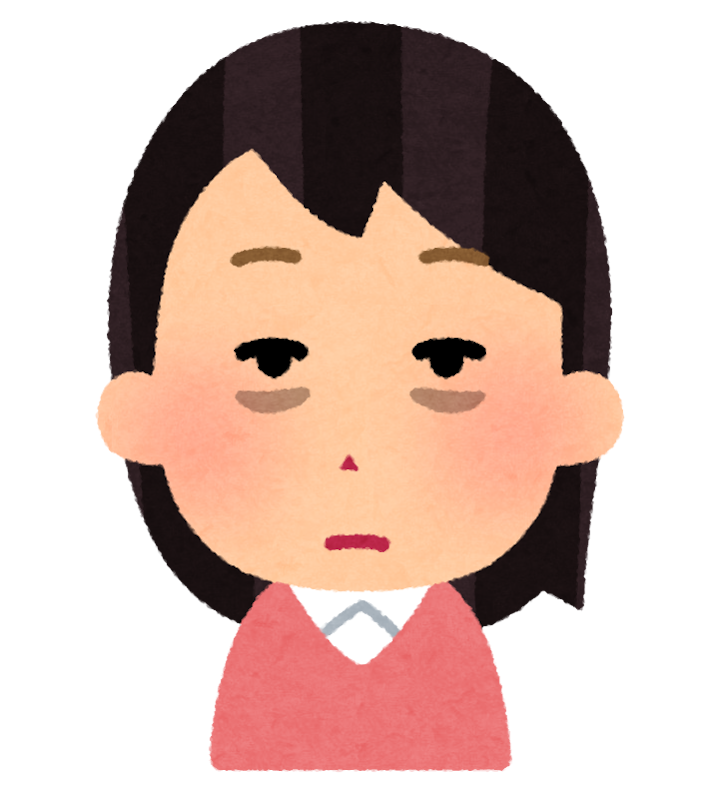
3つ目の学習性無力感になりやすいタイプは、生活リズムが乱れている人です。
- 寝る時間は決まってなくて、いつもバラバラ
- 寝ても疲れがとれない
- 朝起きるのがつらい
このような生活リズムが乱れているタイプは、記憶が定着しにくいばかりか、気分が落ち込み、心身が疲弊し、物事をポジティブに考えてしまいます。
西野精治さんが書いた、『スタンフォード式 最高の睡眠』(サンマーク出版)では、「睡眠不足ん影響」には次のようなものがあると記されています。
- 脳と体が十分に「休息」できておらず、疲労が着実に蓄積している
- 「記憶」の整理がままならず、覚えたはずのことが頭に定着していない
- 「ホルモンバランス」の調整がうまくいかず、肌が荒れたり、体重が増えたりする
- 「免疫力」を高く保てず、病気になるリスクが上がる
- 「脳の老廃物」が除去されず、神経疾患、ひいては認知症のリスクも増加
また、様々な病気のリスクが高まるばかりか、死亡率が上がるというデータもあるそうです。
生活リズムや睡眠の質を高める方法については、下記の記事で詳しく述べていますが、まずは、寝る時間と起きる時間を毎日統一するようにしましょう。
心身が疲れていると、行動する活力も沸かず、無気力の状態になってしまいます。
また、「なにをやっても意味がない」とポジティブにしか考えられなくなってしまいます。
まずは、「とうやったら疲れを取ることができるか」ということだけを考え、心身ともに健康の状態で勉強に取り組むようにしてください。
睡眠に関しては、まずはこちらの【絶対にやってはいけない】睡眠前の『悪習慣』8選がおすすめです。睡眠前の習慣を変えるだけで、睡眠の質は簡単に上がります。
まとめ:学習性無力感を克服すれば面白いように結果が出る
いかがでしたでしょうか。
「どうせ勉強したって成績は上がらない」
「勉強してもなにか良いことが起きるわけじゃない」
このような学習性無力感は、やる気やモチベーション、活力を奪い、「勉強のやる気が起きない」原因となる恐ろしいものです。
もし、今まで勉強で思うような結果が出せていなかったとしても、それは、あなたの能力や才能が否定されたわけではありません。
ただ、「良くない環境で勉強していた」「良くない方法で勉強していた」だけです。
正しい方法や環境で勉強することで、誰でも思うような結果が出せるようになります。
「勉強のやる気が起きない」
「もしかしたら学習性無力感かも」
という方は、ぜひ本記事をよく読み、実践してみていただけると、幸いです。
【東大院生おすすめ】効果の高い勉強法10選【場所やアイテムも】
【東大院生が実践】コントロール感で勉強のやる気を高める方法
「勉強にご褒美」はあり?なし?ありだけど、注意が必要です!
【東大院生が実践】「勉強のやる気が起きない」を心理学で解決!
【東大院生直伝】早朝にパッと起きて、ビシッと勉強する方法5選
【東大院生が教える】完璧主義はだめ?勉強は力を抜いて!
【東大院生おすすめ!】タイムプレッシャー勉強法で成績がアップする
【東大院生が実践】自己効力感を考慮した目標設定【勉強や仕事に】







>>HOME画面に戻る
>>勉強法の記事一覧へ進む