完璧主義だとどうなる?
勉強において完璧主義は危険だ
— 東大院生くろまあくと@作家・ブロガー🌸『東大院生が実践した 超ショートカット勉強法』重版出来🌸 (@akuto_kuroma) 2018年11月24日
なぜなら、一度詰まると時間をかけて理解をしようとするからだ
すると、参考書が最後まで終わらないし、進まないから勉強が嫌いになってしまう
初めから、全てを理解するのは無理だと割り切って、早く、何周もした方が結果的に効率が上がる
このように、勉強において完璧主義は危険であることが多いです。
「頑張っているのに結果が出ない」
「たくさん勉強しているのに点数が伸びない」
このような、悩みを抱えている人は、勉強法が間違っているかもしれません。
- 教科書は初めのページから順番に読む
- 問題集で簡単な問題もとばさないで解く
- ノートはきれいにとらないと気がすまない
- 分からないところがあると時間をかけて理解しようとする
これが完璧主義の人の特徴です。
完璧主義の勉強法だと、時間がかかります。
参考書を読んでいても、”わからないところを放っておかない”ので、全然進みません。
勉強が進まないと、勉強が嫌いになってしまいます。
では、どのように勉強すればいいのでしょうか?
例えば、次のような勉強法が挙げられます。
- 出題頻度の高い箇所から勉強する
- 解ける問題はどんどんとばす
- ノートに記録するのは重要な単語だけ
- 分からないところは一旦とばして、2周目で理解しようとする
このような勉強法は、完璧主義ではなく、効率主義の勉強法です。
完璧主義の人は、勉強をしてること自体に美徳を感じます。
効率主義の人は、短い勉強時間で結果を出すことに美徳を感じます。
「もしかしたら私完璧主義かも・・・」
「少し当てはまるところがあるかも・・・」
という方は、完璧主義から効率主義の勉強法に変えるだけで、簡単に成績がUPしますよ!
それでは、完璧主義から効率主義へ変わる方法をみていきましょう。
完璧主義によるデメリットは、こちらの【頭が悪くなる】完璧主義勉強法のデメリット7選「今すぐやめよう」の記事でまとめています。合わせてご覧ください。
完璧主義から効率主義の勉強へ
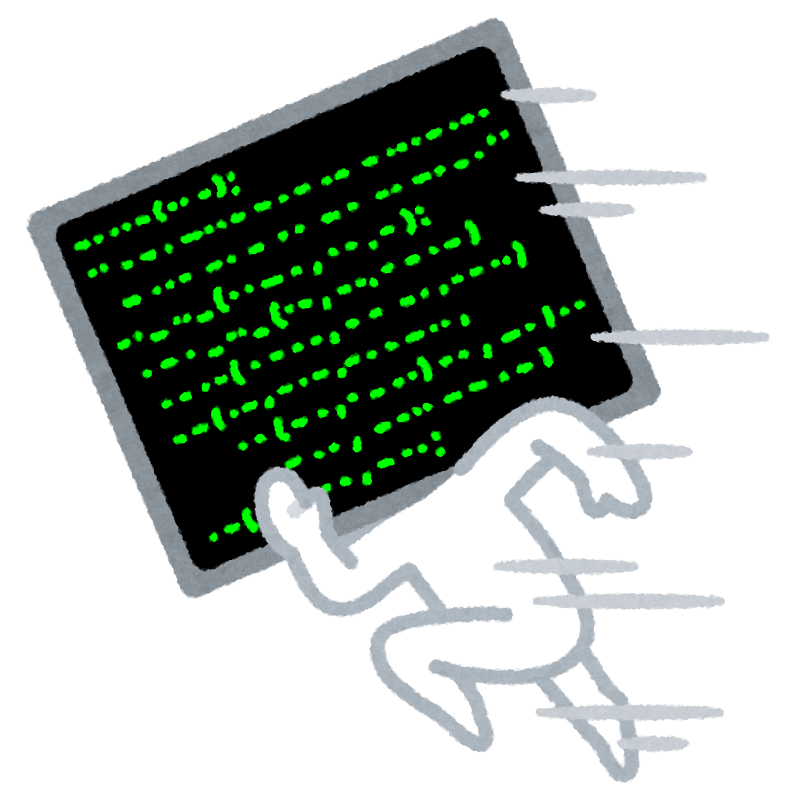
・完璧にやらないと気がすまない
・勉強すること自体に美徳を感じる
・常に効率を重視する
・短い勉強時間で結果を出すことに美徳を感じる
限られた時間の中、勉強で結果を出すためには、完璧主義から効率主義の勉強法に変える必要があります。
それでは、効率主義の人の勉強法を3つご紹介します。
参考書の1周目はかなりテキトーに
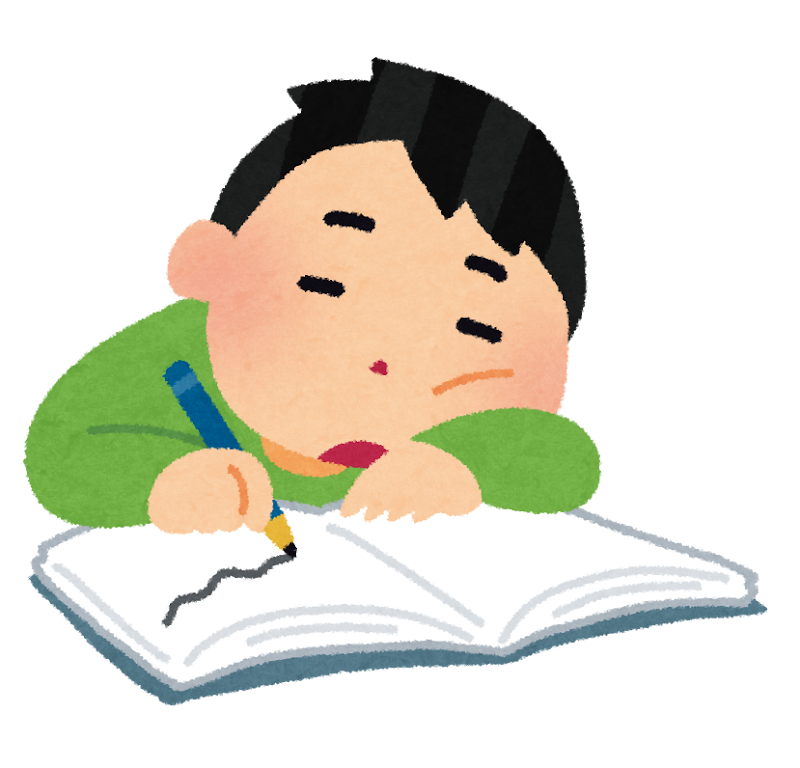
完璧主義の人は、わからない箇所も1度で理解しようとしてしまいます。
すると当然、1時間かけて数ページしか進まない、終わりが見えない状態になってしまい、モチベーションややる気が損なわれます。
勉強する気が起きないと、さらに進むスピードは遅くなり、どんどん悪循環に陥ってしまいます。
私がおすすめしているのは、「参考書は1周目こそ、最もテキトーに」です。
エビングハウスの忘却曲線によると、人は1日後には70%近くのことを忘れてしまいます。
参考書を1周するのに、何週間もかけていたら、一周し終わった頃にはほとんどの内容を忘れてしまっているでしょう。
暗記の基本は、「速く、何周も」です。
「じっくり、1周」では、時間がかかるばかりか、ほとんどのことを忘れてしまいます。
- 日本史や世界史であれば、1周目は太字を流し読みする
- 英単語帳であれば、どんな単語が記載されているのか、パラパラと確認する
1度パラパラ確認しておくだけで、「この単語見たことあるぞ!」と脳が反応し、集中を維持したまま取り組めるようになります。
勉強のやる気がおきない原因は、勉強がなかなか進まないことですので、「速く、何周も、テキトーに!」を意識して勉強するだけで、どんどんやる気がアップしていきます。
参考書を大量高速回転させるメリットはこちらの【高速大量回転記憶術】脳はなぜ繰り返さないと覚えられないのか?の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
まずはじめに過去問題集を確認する
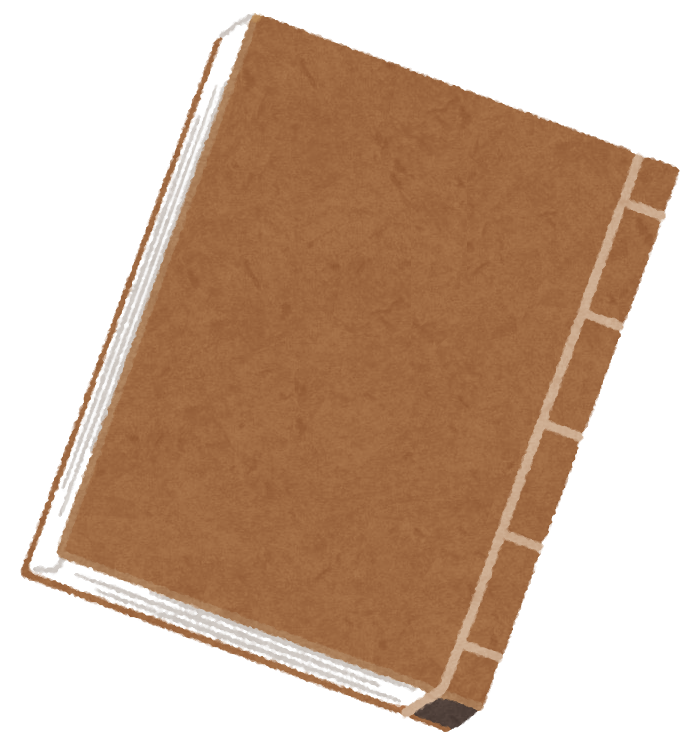
受験勉強や資格試験などの勉強を始めるとき、まずはじめに過去問を確認することが重要です。
過去問とは、すなわち勉強のゴールです。
教科書や参考書、問題集から取り掛かる人がほとんどですが、ゴールが見えていないと正確な道程を思い浮かべることもできません。
また、なんといっても効率が落ちてしまいます。
参考書をはじめから始めるよりも、出題頻度の高い問題から覚えたほうがよほど短時間で目標を達成することができますよね。
まずは過去問を確認し、「最終的にどんな問題を解くことができればいいのか」を確認しましょう。
同時に、問題傾向、記述か・マーク式か、出題頻度の高い問題、なども把握するようつとめます。
出題傾向を把握せずに、参考書を最初から順に解いていくと、次のような勉強時間配分になります。
- 出題頻度(高):30時間
- 出題頻度(中):30時間
- 出題頻度(低):30時間
一方、過去問をチェックしてから、参考書を順に解いていくと、次のような勉強時間配分にすることが可能です。
- 出題頻度(高):50時間
- 出題頻度(中):30時間
- 出題頻度(低):10時間
どちらのほうが効率が良いかは一目瞭然です。
ゴールまでの最短距離を確認するために、まずは過去問題集の確認をするようにしましょう。
こちらの【院試は過去問命】東大合格者はなぜ参考書より過去問を優先するのかの記事は院試を例にしていますが、過去問が大切な理由がわかる内容になっています。
ときには問題を解かず解説をみる

効率を意識するのであれば、「ときには問題を解かずに解説をみてしまう」ことも重要です。
- Aさん:「解き方がわからない問題を1時間粘って考える」
- Bさん:「分からないので、すぐに解説をみる。次は解けるように解き方を覚える」
Aさんは立派です。
ときには、わからない問題でも粘って考えることも重要ですが、その1問を解けるようになるために1時間もの時間を費やしてしまっていることになります。
一方、Bさんのように、分からない問題の解説をすぐにみる場合は、実際に解説をみながら手を動かす時間を考えても15分程度でその問題を解けるようになるでしょう。
「模擬試験で1点でもいい点数を取る!」
この考えは立派ですが、そのために1時間も時間をかけるとなると、「なるべく早く資格試験に合格する」という目標から考えるとずれていますよね。
模擬試験はあくまで模擬試験です。
「模擬試験で1点でも多くとるための勉強」と「本番の試験で1点でも多く取るための勉強」は異なるのです。
目先の気持ちに捕らわれて、ゴールを見失わないようにするのが、効率主義の勉強法です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
勉強すること自体に美徳を感じる、完璧主義の勉強は、言ってしまえば頭をつかわない勉強です。
- 教科書は初めのページから順番に読む
- 問題集で簡単な問題もとばさないで解く
- ノートはきれいにとらないと気がすまない
- 分からないところがあると時間をかけて理解しようとする
これはすべて、目の前のことにのみ没頭している状態です。
すなわち、「集中して勉強している」「頑張って勉強している」ことを良い勉強だと思っているのでしょう。
だからこそ、上述したように無駄な勉強が多く、手間も時間も余分にかかってしまいます。
もし、「少しでも当てはまるかも」と思うのであれば、頭をつかって勉強するようにしましょう。
つまり、以下のようなことを考えながら、どれくらいどんな勉強をするかを自分自身で考えるのです。
- この勉強は本当に必要か
- この勉強法は本当に正しいか
- もっと先に学ぶべきことはないか
- どの問題から解くのが効率が良いか
頭を使う、効率主義の勉強です。
「勉強をすること自体」に頭を使うことは、誰にでもできます。
「どんな勉強をするか」に頭を使うことができれば、あなたの成績はすぐにあがっていくでしょう。
この記事で伝えたかったことは、「勉強には抜け穴があるよ」ということです。
完璧主義で肩に力が入った状態では、抜け穴を見つけることはできません。
肩の力を抜いて、「楽する方法はないかなぁ」とリラックスしながら勉強をするほうが、勉強自体も楽しくなり、どんどん勉強で結果を出せるようになるでしょう。
この記事を機に、「完璧主義」から「効率主義」の勉強を意識していただけると、幸いです。
完璧主義のデメリットは、【頭が悪くなる】完璧主義勉強法のデメリット7選「今すぐやめよう」の記事で紹介しています。
完璧主義をやめるべき理由がより分かると思いますので、合わせてご覧ください。







>>HOME画面に戻る
>>勉強法の記事一覧へ進む